前回のブログでエアインテーク内にブローバイオイルを発見。
これはちょいとよくないな‥‥
どうやらコペンに搭載しているJB-DETはブローバイが多いらしい。
っていうかダイハツ車は多いらしい。
そもそもコペンのブローバイガスの流れはどうなっているのだろう?
それを勉強してみた。
・ブローバイガス
ブローバイガスは、ピストンとシリンダーの隙間から吹き抜けた未燃焼又は燃焼ガスのことで、水分を含む色んな成分が入った有害な物なので大気放出せずに再燃焼させなければならない。
このブローバイガスはクランクケース内の圧力に大きな影響を与える。
ガスが溜まるとクランクケース内部の圧力が上昇し、ピストンの上下運動の抵抗となり、高回転になると数馬力の差となる。
ターボ車はクランクケース圧力が高くなり過ぎるとターボからのオイルリターンが戻りにくくなることでターボチャージャーの潤滑不良が起きてタービン焼き付きの原因にもなり、さらに圧力でターボシャフトからオイル漏れを起こしてマフラーから白煙を吹く等の原因にもなる。
ブローバイガスは新しいエンジンよりも磨耗の進んだエンジンや、ピストンリングの張力の弱ったエンジンほど多く出る。
また、適正な温度よりも低い場合はピストンとシリンダーのクリアランスが大きめになりがでブローバイの発生が多くなる。
同型エンジンでブローバイガスの少ないエンジンほどコンディションが良いって事だ。
つまり、ブローバイの多いエンジンはそれだけオイルを汚染・劣化させてしまうので短いサイクルでオイル交換をしてあげる必要がある。
オイルを劣化させる要因はこのブローバイガスによる汚染が強く、各部の磨耗などによる金属粉などはそこまで影響しない。
また、ローテンプサーモを使用すると平常時から水温が低くなり、エンジンの最適温度域を外れて、シリンダーのクリアランスなどが適正でないためにブローバイの吹き抜けなどが多くなり、しかも温度が低いことからブローバイに含まれる水分や生ガス分の揮発が悪化する。
結果的にオイルを希釈、汚染し、エンジンオイルの寿命を縮めることにつながります。
悪い事ばかりなのでブローバイは効率よく抜くようなシステムになっており、シリンダーヘッドなどからインテーク内に戻して再度エンジンに吸引・燃焼させる。
ここで重要になってくるのがPCVバルブだ。
簡単に言うと、サージタンクが負圧なら開いて、正圧なら閉じてる。
サージタンクの状態が支配的だ。
もちろんNAとターボでは閉じ具合が違う。
 |
| PCVバルブの動作 |
・サブの系統
サージタンクに直結しており中間にPCVバルブがあり、アイドリング等スロットルバルブが閉じている状態(サージタンク内部負圧が強い場合)では開通している。
スロットルバルブが開いている時はPCVによってここの通路は閉じられる。
・メインの通路
ヘッドカバーからエアクリーナー後~タービン前まで戻っている通路でこれにはチェックバルブは入ってない。
スロットルを開けて、インテーク内部の流速が上がってそれにより引っ張られてクランクケースからブローバイを吸い出す。
・アイドリング時やエンブレ時
サージタンク内負圧が強いので(低負荷)、PCVバルブが開通しており、エンジン内のブローバイガスを吸込む。
また、メイン系統のブローバイホースからはエアクリーナーを通過した綺麗な空気をクランクケース内に取り込んでエンジン内部を換気することでエンジン内の清浄とエンジンオイルの劣化を防いでいる。
 |
| アイドリング時の流れ |
・街乗り加速時
街乗り加速中はサージタンク内は弱い負圧~大気圧くらい。
当然、負圧の強さによってブローバイガスの流れは可変する。
また、インマニは空気の流れが速くなるのでその負圧によって(ベンチュリー効果)メイン系列からもブローバイガスが引き抜かれる。
 |
| 街乗り加速中 |
・ブースト加速時
サージタンク内は正圧。
よってPCVバルブは完全に閉じる。
インマニの負圧(ベンチュリー効果)によりメイン系列からブローバイガスが引き抜かれる。
 |
| ガンガン加速中 |
これがコペンのブローバイガスの流れね。
で、ここまで書いていてあることに気が付いた。
これ、絵が分かりずらいな。
メイン系統はターボ前に戻る、というのを図に書いていなかった。
メイン系統はターボ前に戻りまっせ。
まぁそんな感じでもしかしたらPCVバルブの不良が疑われるな…
とりあえずパーツクリーナーで綺麗にしたけどこれも消耗品だから新しいの買って交換しよう。
ってなわけで交換した。
おまけ
・オイルキャッチタンク
ブローバイガスにはエンジンオイル等のミストが含まれているので、インテーク内やインタークーラー内はオイルが付着している場合が多い。
これを少しでも低減させるためにメイン通路の中間に、気体成分と液体成分を分離する装置を付ける。
これがオイルキャッチタンクだ。
このオイルキャッチタンクは本来はレースにおいてエンジンブローや転倒したときなどにコースにオイルをまき散らさないようにするためのものだ。

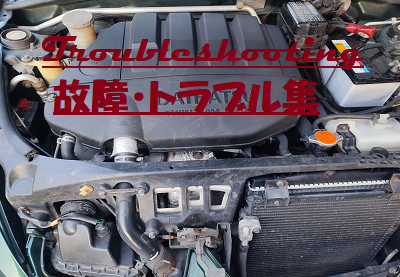



.jpg)

